
6月21日に与那原町当添漁港で行われたハーリーにいって来ました。
当添ハーリーは、明治41年頃から始まり、昭和39年まで開催してましたが、一時中断している時期があり、再び昭和54年から開催し今年が第31回目になります。
当添ハーリーの様子
参加するチームは、本日のレースのスケジュール表に記載されています。小学生対抗、PTA対抗戦、女子対抗戦、職域対抗戦、などがあります。
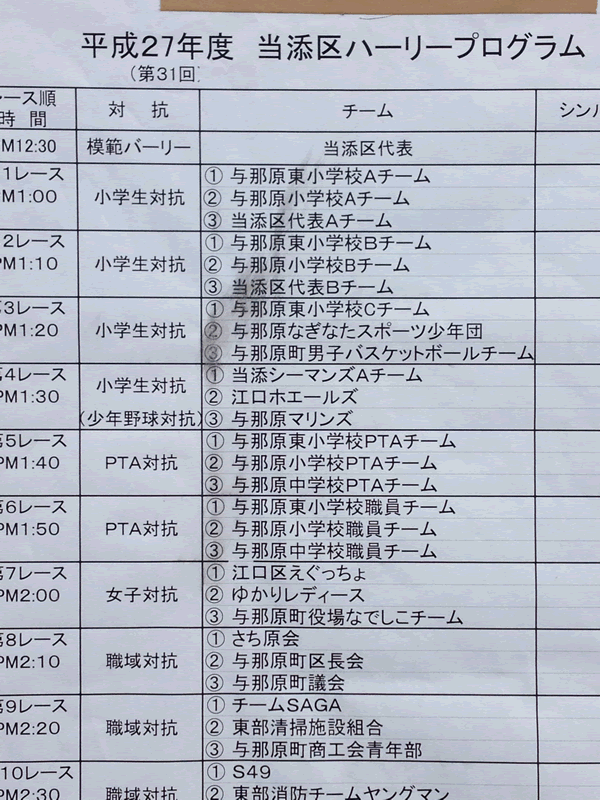
さぁースタートです!3隻で競い合います。

場内では実況放送が流れるんですが、その実況は2人の男性が担当していて、その2人の掛け合いのトークが面白い!
外国から留学に来ている高校生や本土から沖縄に移住した人などにインタビューして、笑いを交えて紹介して場内を盛り上げみんな爆笑!
会場を盛り上げなければならないから実況って大切なんだなぁーと実感。あの2人面白いけどお笑い芸人?なのか。。。

あっ!転覆した!この日のお天気は曇り。冷たそう。。。

実況も 「転覆しましたね!さぁーここからが見せどころ、舟を元に戻すことができるでしょうか!」と挑発。するが・・・・待機していた救助隊がすばやく救助に向かいます!

実は、この転覆は沖縄のハーリーでは恒例。 かつて、転覆しやすいサバニで漁をしていた漁師は、転覆してもすぐに舟を起こし漁を続けていたんだそうです。
その海人の力強さをお客さんの目前で披露するようになったのがはじまりなんだそうです。
沖縄ではどこのハーリーでもわざと舟を転覆させて観客を楽しませてくれます。ですが現在は海人だけが参加しているわけでは無く一般の人も多いので転覆したらすぐに救助が助けます。安心して参加できますよ。
当添ハーリーではこの日、すべてのプログラムのレースが終了すると 「体験したいお子さんは集まってください!」と場内放送が、希望したお子さんはサバニに乗って実体験ができます。
見ていて思ったんだけど、参加したらさらに楽しさも倍増するのかもって思いました!誰でもチームを作って申し込めば参加できるそうなのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
大規模なハーリーも良いけど、当添ハーリーはこじんまりとして温かさがあって、凄く楽しかった。実況のお二人さんが盛り上げて面白かったなぁー!おつかれさまでした。また来年も見に来よう!
ハーリーについて
沖縄では、毎年5月のゴールデンウィーク中に開催される『那覇ハーリー』を皮切りに、6月、7月になると、各地でハーリーが行われ沖縄の夏はさらに熱く盛り上がります。
沖縄でハーリーが行われるようになったのは、600年も前の琉球王朝時代に中国から伝わったと言われており、豊漁と海上安全を祈願するのが目的の海人(うみんちゅう)の「海の神事」。
現在は、観光イベントとしても人気が高く、大規模で行う『那覇ハーリー』や伝統を守り続けている『糸満ハーレー』は、さまざまなイベントも用意されており、観光客も多いので知っている方も多いのではないかと思います。
ところで、お気づきになりましたか?
那覇は・・・ハーリー
糸満は・・・ハーレー
と、呼び方が違います。
どう違うのか気になってので調べてみると、意味はどちらも同じで、爬竜船(はりゅうせん)を漕ぎ競い合う行事のこと。
現在、沖縄では「ハーリー」と呼んでいる地域が多いのですが、糸満では、昔からの沖縄方言で呼ぶ「ハーレー」という名前を残したいと言う思いで糸満ハーレーと呼んでいるそうです。
一時期「爬龍船行事」とか「海神祭」と呼んでいたこともあったんだそうですが “ハーレー”と言う呼び方に戻したんだとか。
そうそう、糸満ハーレーにはもう一つの恒例行事が行われていて、それが面白い!『アヒル取り』と言って、港内にアヒルが放たれ、それを海に飛び込み捕まえる行事があるんですが、これは見物客も参加できる行事で、見物している人が次々と海に飛び込み必死にアヒルを捕まえようとする姿が面白い!捕まえたアヒルは持ち帰る事もできるんですよ。
ハーリーに使用される船について
ところで、ハーリーに使用される舟ですが、装飾がきれいでとっても特徴がありますよね。
那覇ハーリーで使用されているのは、舳先と船尾に龍の彫刻が施された鮮やかな爬竜船(はりゅうせん)を使用。この爬竜船は全長14.55メートルで、漕ぎ手は32名、鐘打ち2名、舵取り2名、旗持ちなど6名と乗船者は42名と大型です。
多くの地域では、小型漁船の「サバニ」を使用しているところが多く、サバニの大きさは地域によってさまざまですが、漕ぎ手が10名程度、舵取り1名が乗船して競い合うところが多いそうです。
![]() この記事は私が書きました♪
この記事は私が書きました♪

しのげっと♪プロフィールはコチラ
今まで一度も沖縄に来たことが無いのに旦那の思いつきから、2011年5月23日突然、沖縄に移住!知り合いも居ないし、仕事も無いし、とっても不安!でもなんとか・・・頑張って沖縄を満喫しています♪♪
